ネット問い合わせ全盛時代に何が起こる?
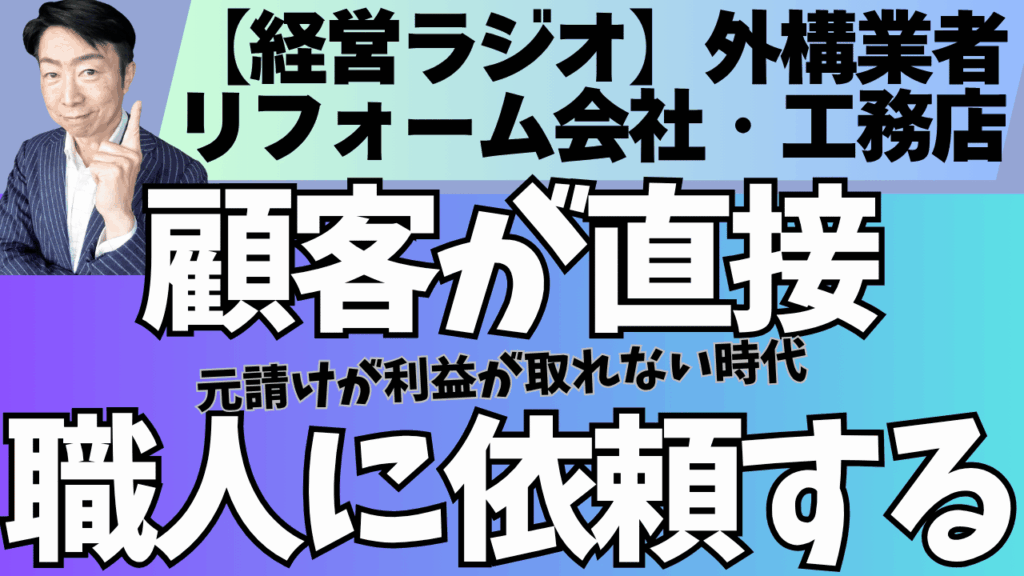
施工会社を飛び越え「デザイナー・プロデューサー・職人へ直接発注」が当たり前になるのかを考える
こんにちは。アルクス株式会社の上内隆之です。
ここ数年で「まずは SNS やマッチングサイトから問い合わせ」という施主が激増しました。
この流れが進むと――
- 外構デザイナー
- 建築デザイナー
- 建築プロデューサー(PM)
- 現場監督・職人個人
に 直接発注 するケースが主流になるのでは? という声が業界内外で聞こえてきます。
本稿ではそのシナリオを肯定・否定の両面から深掘りし、
外構業者・工務店が取るべき戦略を提案します。
1️⃣ ネット発注が変える建築バリューチェーン

スマホ世代が求める “透明性” と “選択権”
- 施工会社の見積はブラックボックス → 中間マージンを嫌う
- SNS で「この職人に頼みたい」「このデザイナーの世界観が好き」と指名買いが可能
マッチングプラットフォームの台頭
| プラットフォーム | 主な特徴 |
|---|---|
| sui-reno, TruckWorks | 職人・現場監督個人を直接検索 |
| ARCHITREND MOOV | 建築家+工務店をセット提案 |
| STORES住宅版 (β) | デザイナーがオンラインで概算見積 |
示唆:プラットフォームが設計と施工を分離→再統合する動きを加速させる。
2️⃣ もし直接発注が主流化したら業界はどうなるか?

工務店・外構業者は「施工管理BPO」化
- 図面・工程・コスト管理のみ請負い、現場には専門職人チームが流動的に集まる
- 会社の利益源はマネージメントフィー+保証料にシフト
職人ブランド化と価格の二極化
- SNSフォロワー数=単価を決める時代。人気職人は1日10万円超も
- 一方で汎用技能はプラットフォーム競争で単価下落の恐れ
施主リスクとプロジェクト分散
- デザイナー・職人が契約単位で点在 → 瑕疵責任の所在が曖昧
- 問題発生時に「誰が総合窓口か」不在になりやすい
3️⃣ それでも “ワンストップ請負” がなくならない理由
法的責任と瑕疵担保
- 住宅瑕疵保険・建設業許可は元請けが窓口
- 直接契約パーツの寄せ集めでは保険加入不可ケースも
工期・予算・近隣対応の複雑さ
- 小規模でも10業種以上が関与 → 施主が進捗管理を担うのは現実的でない
- 近隣クレーム対応・追加変更の調整など、“泥臭い部分”を引き受ける主体は必要
結論:
完全分散モデルは一定層で伸びるが、保証と管理のワンストップ需要も残り続ける。
4️⃣ 小規模施工会社が取るべき 3 つの戦略
① 自社も「顔が見える専門家ブランド」を打ち出す
- 代表・現場監督・職人をSNSで個人発信 → 指名受注チャネルを自社で確保
- HPにスタッフの得意分野・施工事例をプロフィール形式で掲載
② デザイナー・職人とのアライアンスを組む
- パブリックなSlack / LINE OpenChatでプロジェクトベースのチームを即結成
- 紹介料・アフター保証の取り決めを業務委託契約テンプレで標準化
③ プロジェクトマネジメント+10年保証を武器に
- 施工管理クラウドで進捗・原価を可視化 → 施主もリアルタイム閲覧
- 保険会社と提携し、分離発注でも一括瑕疵保証をセット販売
意外と盲点:直接発注時代でも“現場調整力”はレアスキル
- 設計図面通りに収まらない現象=“現場アジャイル”
- 問題解決スピードがプロジェクトの成否を決める
- ここを担える工務店・外構業者は高単価PMとしてポジションを確立できる
まとめ:分散か?ワンストップか? “選ばれる軸” を今決める
| 方向性 | 必要アクション |
|---|---|
| 分散発注の波に乗る | 個人ブランド強化/アライアンス構築 |
| ワンストップ請負を極める | デジタル管理+保証パッケージで差別化 |
「自社に最適なポジショニングを相談したい」「分散モデルの契約スキームを整えたい」
月5万円からの経営顧問サービスで、戦略設計から運用まで伴走します。
アルクス株式会社へのお問い合わせはこちら
―― ネット発注時代も“選ばれる会社”を一緒に作りましょう!
著者:アルクス株式会社 上内隆之
-198-x-50-px-519-x-160-px-198-x-50-px.png?1762312251)


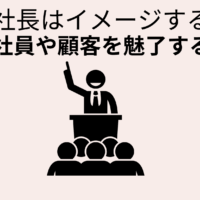
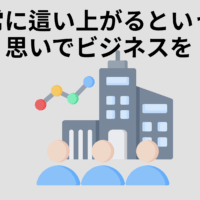
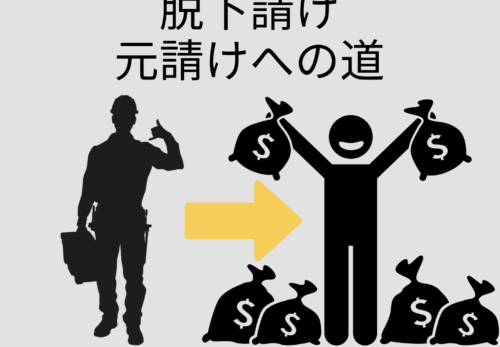
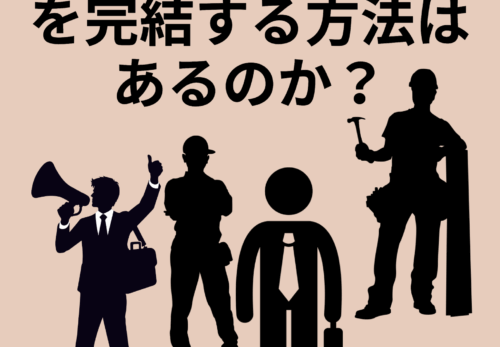




-198-x-50-px-519-x-160-px-519-x-144-px-2.png?1762312251)
この記事へのコメントはありません。