建築業界が大きく変わっていく まず何が変わるか?
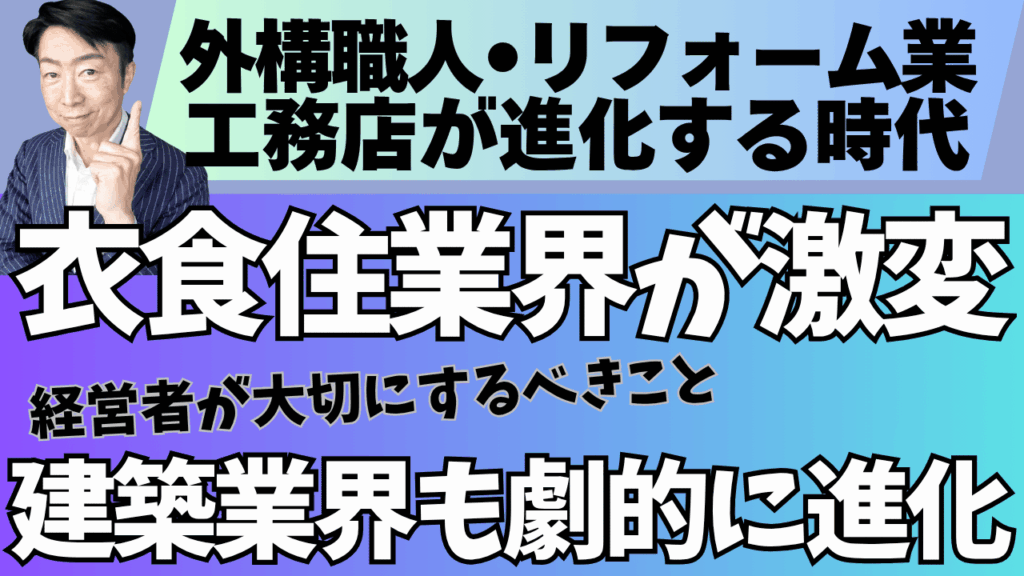
今、建築業界では大きな変化の波が押し寄せています。新築住宅の需要は長期的に減少傾向にあり、2024年の新設住宅着工戸数は約79.2万戸と、前年からさらに3.4%減少しました。
年間100万戸超えが当たり前だった時代から比べると、住宅市場の縮小は明らかです。特に注文住宅(持家)の着工戸数は1960年以降で最低水準を記録しており、物価高による消費者マインド低下も影響しています。
同時に、ウッドショックや円安・ウクライナ情勢などに起因する資材価格の高騰、労務費の上昇が中小企業の収益を圧迫しています。工事契約時に想定していなかったコストアップを価格転嫁できなければ、工事ごとに赤字が出るリスクすらあります。実際、2024年の建設業倒産件数は1,942件とここ10年で最多を記録し、中小の建築会社に厳しい現実を突きつけています。
さらに、集客や営業の手法も様変わりしました。一昔前は住宅展示場やチラシ、知人の紹介が主流でしたが、今や多くの施主様はインターネットやSNSで情報収集し、工事店を比較検討しています。口コミサイトの評価をチェックし、YouTubeで施工者の人柄や実績を確認してから問い合わせるお客様も珍しくありません。言い換えれば、デジタルを活用できない会社は潜在顧客との接点自体を失いかねない時代になったのです。
このように市場規模の縮小、コスト構造の悪化、顧客の購買行動の変化という三重の変化が、中小建築業者の経営を取り巻いています。では、この激動の中で生き残り、成長していくためには何が鍵となるのでしょうか。その答えの一つが、次に述べる「中間マージンの見直し」と「顧客の共感を得る経営」なのです。
余計なものがあり過ぎ? 中間マージンが必要ないでしょ?

住宅業界には昔から、多層構造の商習慣があります。元請け会社が営業・集客を行い、実際の施工は下請け業者に依頼するという形です。この際、元請けや仲介業者は紹介手数料として工事費に上乗せをします。その中間マージンは工事金額の10〜30%にも達する場合が多く、お客様に提示される見積価格も本来より高くなりがちです。例えば100万円規模のリフォーム工事なら、中間業者が介在するか否かで最終価格が30万円以上違ってくることもあります。
しかし、果たしてこの中間マージンは本当に必要なものでしょうか?お客様から見れば、施工そのものに関係ないコストはできるだけ省きたいと考えるのが当然です。実際、最近では「自社施工・中間マージンなし」をセールスポイントに掲げる工務店やリフォーム会社も増えてきました。インターネットで直接業者に依頼できる環境が整ったことで、余計な中抜きコストを削減し、適正価格で質の高い工事を提供するという新しいモデルが浸透しつつあります。
中小の建築会社にとっても、中間業者に頼らず自社でお客様と直接つながることが利益体質への第一歩です。中間マージンを削減できれば、その分をお客様に値引き提供して受注競争力を高めるか、あるいは適正な利益として社内に蓄えることができます。もちろん、自社集客にはWebサイトの運営や広告など新たな取り組みが必要になりますが、それらは一度軌道に乗せれば将来的な資産となり続けます。無駄なコストを払い続けるのではなく、将来の集客基盤を作るためにリソースを投下する——この発想転換が、これからの時代に求められているのです。
魅力的な会社になって、良い家を作るカタチがあって、良い施工をして 満足度の高いアフターフォローがあれば 多くの顧客は共感してくれる

価格競争に陥らず安定的に受注を増やすには、会社そのものの魅力を高めて「ファン」を作ることが近道です。お客様は単に安いから契約するのではなく、「この会社になら任せたい」「この人たちと家づくりをしたい」と感じて契約するものです。そのためには、御社がお客様から共感される存在になることが重要です。具体的には次のようなポイントが挙げられるでしょう。
- 魅力的な会社であること:社長の想いや会社の理念が明確で、地域や社会に貢献したいというビジョンが伝わる会社は、それだけで応援したくなるものです。社員が誇りを持って働き、会社全体に活気があるといった雰囲気も大切です。
- 良い家を作るための仕組みがあること:自社ならではの工法やデザイン力、品質管理の徹底など、「良い家を提供するためにこんな工夫をしています」という型があると差別化につながります。例えば独自の施工マニュアルや、定期的な技術研修制度などは、お客様にも安心感を与えます。
- 良い施工を実践していること:現場での丁寧な仕事、近隣への配慮、安全管理の徹底など、施工品質そのものが高いことは言うまでもなく重要です。いくら安くても雑な施工をする会社には依頼したくない、というのが顧客心理でしょう。
- 満足度の高いアフターフォローが万全なこと:引き渡したら終わりではなく、定期点検やメンテナンス、リフォームの相談対応など、長期的なお付き合いを大切にする会社は信頼されます。「この会社に頼んで良かった」とお客様に心から思ってもらえれば、リピートや紹介にもつながります。
上記のような要素が揃っていれば、お客様は価格以外の部分で御社に大きな価値を感じてくれます。共感や信頼でつながった関係性は簡単には揺らぎませんし、たとえ多少価格が高くても「この会社にならお願いしたい」という強い動機になります。結果として受注単価も利益率も向上し、経営に余裕が生まれる好循環が生まれるのです。
① とにかく安くして仕事を取って、薄利で苦しむ建築会社
残念ながら、多くの中小建築会社が「仕事を取るため、とにかく価格を下げる」という戦略に陥っています。一見合理的な方法に思えますが、これは終わりなき消耗戦になりかねません。他社が値下げすればこちらもさらに下げざるを得ず、利益はますます削られていきます。薄利どころか赤字ギリギリの受注が増えれば、少し材料費が高騰しただけで赤字転落するリスクも高まります。
薄利で受注を重ねる会社では、現場スタッフも疲弊しがちです。利益が出ないために人件費を抑え、少人数で現場を掛け持ちすればミスも増えます。アフターフォローに手が回らず、お客様からクレームを頂くこともあるでしょう。その結果、せっかく苦労して受注しても次につながらず、いつまでも新規客獲得に奔走しなければなりません。まさに安かろう悪かろうの悪循環で、経営者にとっても従業員にとっても苦しい状態が続いてしまいます。
こうした薄利多売の延長線上に待っているのは、事業の行き詰まりです。前述のような外部環境の変化も相まって、近年は中小の工務店や建築会社の倒産が増加傾向にあります。価格だけで勝負するやり方には明確な限界があり、早急にビジネスモデルを転換しなければ生き残れない時代に入っていると言えます。
② 顧客から共感を得た建築会社は依頼が殺到している
一方で、顧客の共感を得る経営に成功した会社には仕事の依頼が殺到しています。例えば、あるリフォーム会社は「誠実で丁寧な仕事ぶりと心温まる顧客対応」で地元の評判を集め、紹介だけで毎月安定した受注を得るようになりました。価格競争とは無縁で、むしろ「多少高くてもあの会社に頼みたい」というファン客が付いています。施工後のお客様アンケートでも「細部までこだわった提案に感動した」「社長の家づくりに対する熱意に共感した」といった高評価が並び、リピートや紹介につながっています。顧客との信頼関係がブランドとなり、新規広告に多額の費用をかけなくても自然と案件が舞い込む状態です
このように「選ばれる会社」になれば、ビジネスの質が一変します。安値受注のための無理なコスト削減や営業活動に追われることが減り、本業である良い家づくりにリソースを集中できます。社員のモチベーションも上がり、離職率の低下や技術力向上にもつながるでしょう。何より、お客様からの信頼という無形資産は今後の経営の大きな支えとなります。共感を得た会社には好循環が生まれ、持続的な成長軌道に乗ることができるのです。
③ 結局、何を大切にするべきか?

価格競争に陥る会社と、顧客から愛される会社の差は一体どこから生まれるのでしょうか。結局のところ、経営者が何を大切にするかに尽きます。目先の売上を追って安易に値下げしてしまうのか、それとも自社の提供価値を信じて適正価格を貫き、お客様にその価値を理解してもらう努力をするのか。ここが分かれ道です。
大切なのは、自社が本当に提供すべき価値を見極めることです。他社より優れた点、独自の強み、お客様に喜ばれているポイントは何かを洗い出し、それを軸に経営資源を投下しましょう。そうすれば自然と「何をやらないか」も明確になり、無駄な値引きや非効率な営業活動を減らせます。自社の強みを伸ばしオンリーワンになることが、価格競争から脱する近道です。
また、収益面では粗利益の確保を最重視すべきです。売上高よりも「いくら粗利を稼げたか」が会社の体力を決めます。まずは自社の固定費(月々の人件費や家賃、借入返済など)を洗い出し、それを上回る粗利益目標を設定しましょう。例えば人件費が一人あたり月50万円かかるなら、最低でも100万円の粗利を生み出す必要があります。その粗利を確保できる受注単価・工事量を追求し、安易な値下げで仕事量だけ増やすことは避けてください。
最後に、お客様に価格以上の価値を感じていただくためのコミュニケーションも重要です。ただ数字を提示するだけで契約を迫っても、人は動きません。「この会社は自分たちの悩みをわかってくれている」「この提案なら納得できる」とお客様に感じていただいて初めて、適正な価格にご理解をいただけます。そのために、共感を呼ぶ情報発信や丁寧なヒアリングを行い、お客様との信頼関係を築きましょう。価格はあくまで最後の後押しであり、主役ではないのです。
集客と営業代行は私たちプロに任せるべき(月5万円の経営顧問料で成功への道のりを作ります)
ここまで見てきたように、中小の建築会社が薄利体質から脱却するには、無駄なコストを省き(中間マージンの削減)、自社の価値を高めて顧客の共感を得ることが重要です。しかし実際問題として、「自社で集客を強化しようにもやり方が分からない」「ブランド力を高めたいが時間も人手も足りない」というお悩みも多いでしょう。そこで活用していただきたいのが、私たちのような営業・集客支援のプロフェッショナルです。
営業代行や集客支援をプロに任せ、月5万円程度の経営顧問契約で伴走支援を受けるという方法は、非常に効果的です。弊社アルクス株式会社は、建築業界に特化した営業戦略立案・営業代行(BPO)サービスを全国展開しており、企画からリスト作成、アプローチ代行、効果分析までワンストップで支援しています。岐阜・愛知・静岡・大阪・兵庫・三重・奈良・和歌山・千葉・神奈川・沖縄など各地にて対面での経営相談が可能な体制を整え、中小建築企業様の元請け化(直接受注による高収益体質への転換)を後押ししてきました。
まずは弊社の無料経営相談窓口をご活用ください。現在抱えておられる課題をヒアリングし、最適な集客戦略と経営改善プランを提案いたします。その上で、営業代行サービスにより新規顧客獲得を加速し、月5万円の経営顧問契約によって継続的にPDCAサイクルを回していく——そうした組み合わせによる戦略の実践をぜひお試しください。これは弊社が数多くの中小建築会社で実証してきたモデルであり、貴社の持続的成長と成功への近道になると確信しております。
まとめ
中小規模の建築会社がこれからの時代に生き残り、発展していくためには、発想の転換と専門家の力を借りることが欠かせません。市場環境が厳しいからといって安売りに走れば、自社の首を絞めるだけです。そうではなく、自社の強みを武器に顧客の共感を得る経営へとシフトし、プロの支援を受けながら戦略的に集客力・営業力を強化することで、薄利体質から脱却できます。
アルクス株式会社では、日々こうしたテーマでYouTube配信やブログ発信を行い、数多くの経営者様の課題解決に取り組んできました。御社もぜひ、この機会に自社の経営を見直し、一歩踏み出してみませんか。まずはお気軽に、無料経営相談ページよりお問い合わせください。私たちが伴走しながら、御社の「良い家づくり」で利益をしっかり確保できる仕組み作りを全力でお手伝いいたします。
-198-x-50-px-519-x-160-px-198-x-50-px.png?1768533277)

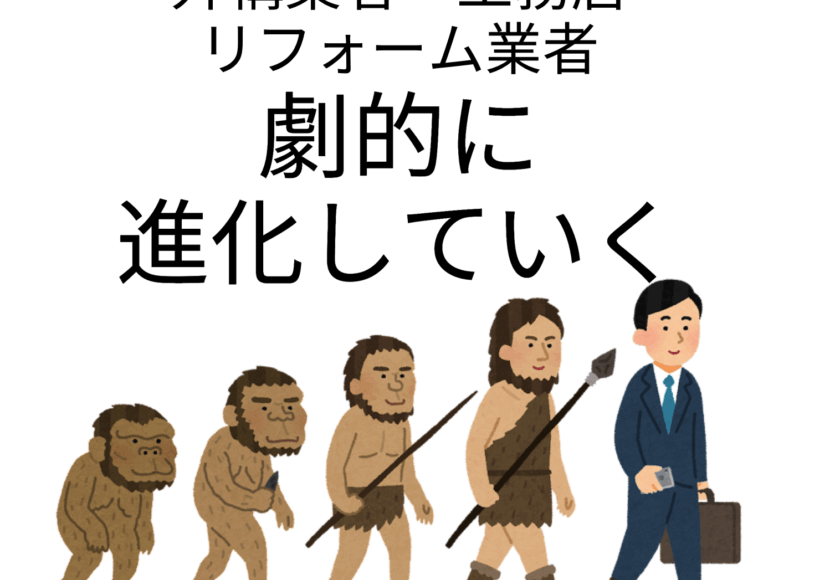
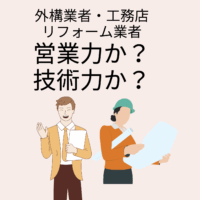


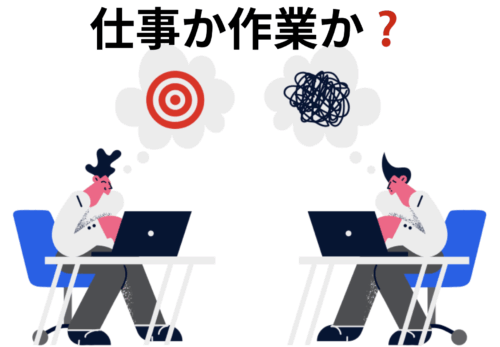


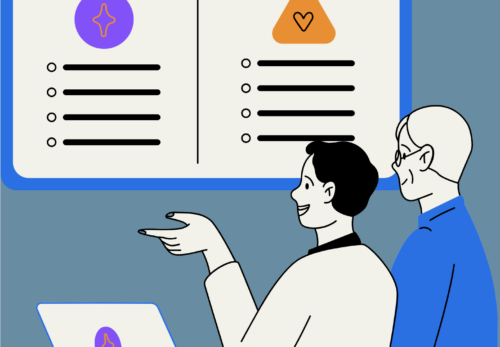
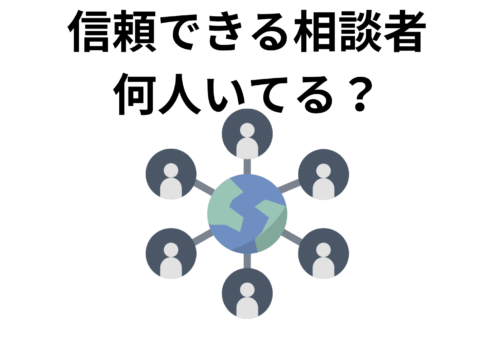
-198-x-50-px-519-x-160-px-519-x-144-px-2.png?1768533277)
この記事へのコメントはありません。