営業代行・集客支援で外構工事会社の元請け化を実現する粗利モデル
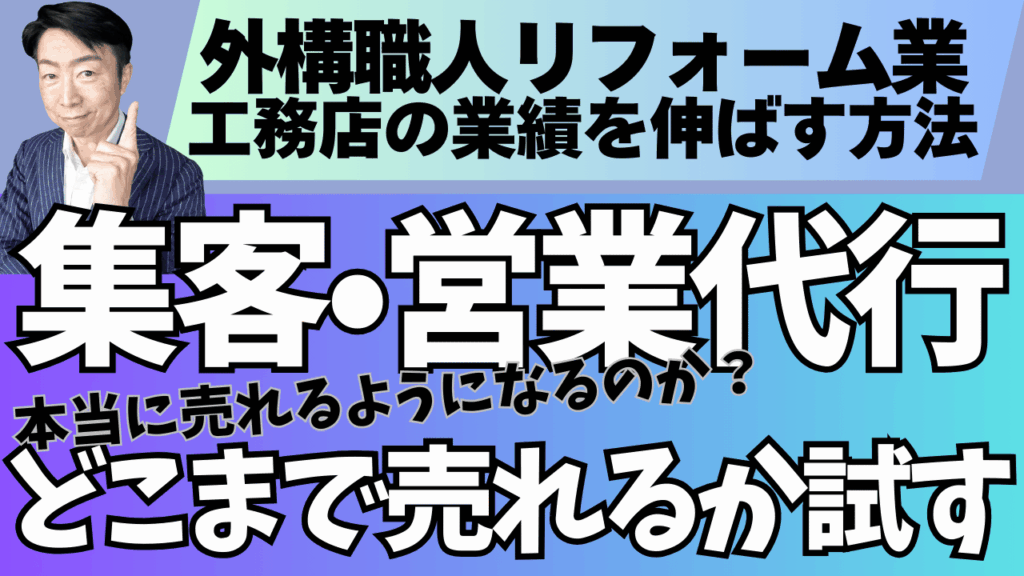
インターネット上での集客はSEO、SNS、広告など多様な手法を組み合わせて行われます。上の図は「Web集客全体図」で、各チャネルがどう顧客獲得につながるかを示しています。自社サイトやGoogleビジネス、SNSで情報発信しつつ、必要に応じてリスティング広告やバナー広告を併用することで、効率的にリードを集められます。これらをプロの営業代行会社に任せることで、建築・外構工事会社の皆様も最終顧客への直接営業が可能になり、従来の下請けから脱却して元請けに近いビジネスが実現します。実際、アルクスでは、営業戦略の立案からリスト作成、リードアクション、分析・PDCAまでワンストップで提供する営業BPOサービスを手掛けています
例えば、Webサイト・SNS・YouTube・Googleビジネスプロフィールといった複数のメディアを活用して集客するモデルが効果的です。上図のように、Webサイトでは「リスティング広告」「バナー広告」「SEO対策」で検索結果から流入を狙い、SNS/YouTubeでは「継続的な投稿」「インフルエンサー依頼」「広告」で幅広い層にアプローチします。Googleビジネスプロフィールも活用し、口コミ対応や最新情報の更新を行うことで地元ユーザーに見つけてもらいやすくします。これらを営業のプロに任せることで、新規顧客獲得のノウハウと人的コスト削減の両立が図れます
上記のように集客と営業活動を強化すれば、従来の元請け依存から脱却し、自社で直接受注できる体制をつくれます。Web集客や広告運用によって自社の施工事例や技術力を広くアピールすれば、設計事務所や不動産管理会社、個人宅など複数の取引先を獲得できます。これにより複数拠点(多店舗)で同じモデルを実行すれば収益は累乗的に増加するため、多店舗展開が有利になります。まずは人件費・広告費など固定費を把握し、それを上回る粗利を目指すことが重要です。例えば人件費が1人あたり月50万円なら、約100万円の粗利(月)が必要という目安があります
あなたの会社は、月にどれくらいの粗利を出せば余裕を持って経営できるのか?

中小企業経営では、まず固定費(人件費・賃料・設備費・借入利息など)と目標利益から逆算して必要な粗利益額を計算しましょう。一般に、粗利額=売上ー仕入原価です。目安としては、人件費を粗利の50%程度に抑える構造が理想と言われています。つまり、人件費1人50万円に対し粗利100万円を確保できれば、会社として余裕が生まれやすいという考え方です。例えば月の固定費(人件費合計+その他経費)が200万円だとすると、20%程度の利益率を見込むと粗利1,000万円以上(月)が必要という計算になります(理想的な経常利益率は粗利率×20%程度)。
これはあくまで目安ですが、計画を立てる上では重要な指標となります。実際には業種ごとに粗利率も異なるので、自社の利益構造を可視化しておくことが大切です。必要な粗利が分かれば、逆に必要な売上高や契約数も導き出せます。以下では例として、新規顧客獲得数と成約率から必要粗利を算出するモデルを紹介します。
毎月15件の集客をして、そのうち30%を成約に至らせると約5件の契約が取れる。 平均工事単価を150万円と設定すると750万円の工事が取れて、そのうち187万円が粗利。 そのうち75万円があなたの取り分になるすれば商売としてありか?なしか?
上記の数値モデルで収益イメージを確認しましょう。
- **リード(商談)数:**毎月15件
- **成約率:**30%(15件中 約5件が契約)
- **平均契約単価:**150万円
- **月間売上:**5件×150万円=750万円
- **粗利益率:**仮に約25%(業界・施工内容により前後)とすると、750万円×25%=約187万円が粗利
- **経営者取り分(利益):**粗利の約40%を経営者報酬とすると約75万円/月
この例では、毎月5件の契約で約75万円が社長の取り分になります。年間ベースでは900万円に相当し、一般的に言われるコンビニ経営オーナーの平均年収700~900万円を上回る水準です。ただしどちらが「大変か」は別問題です。
① このモデルを使うと多店舗展開が有利と思える
上記のモデルは固定費(広告費や営業人件費など)を複数拠点で分散できるため、多店舗展開をすると収益性が高まります。例えば同じ施策を2店舗で実施すれば売上・粗利はほぼ2倍になり、広告単価交渉や資材調達力も向上します。外構工事会社の場合、住宅地や地域によって需要に波があるので、地域を分散することで安定的に案件を獲得しやすくなります。一方、店舗を増やしても下請け体質のままでは利益は増えません。プロに集客・営業を任せることで、各店舗が自社の「看板」施工を直接受注できるようになり、元請け化が進みます。
② コンビニより儲かるがどっちが大変なのか?
外構工事会社のモデルでは先述の通り年900万円超の収入モデルになります。これは世間でよく言われる「コンビニオーナーの平均年収700~900万円」に相当し、数字上は同等か上回ります。しかしコンビニ経営は24時間営業で在庫管理、スタッフ管理、深夜シフトなど仕事量がとにかく膨大です。さらに多くのコンビニチェーンでは売上の一定割合をロイヤリティとして本部に納めねばならず、利益率は思ったほど高くなりません。一方、外構工事会社は代金回収がプロジェクト単位で月末締めなどになるためキャッシュフロー管理が必要ですが、フランチャイズ料はなく、一度の工事でまとまった売上が得られます。ただし繁忙期に作業が集中しやすいので、体力・人手の確保が大きな課題です。
③ コンビニ経営の大変さと外構工事会社の大変さを分解してみる
- コンビニ経営: 仕入れ・発注・棚卸・接客まで業務が多岐にわたり、慢性的な長時間労働になります。近隣店舗との価格競争やサービス競争も激しく、オーナーには責任も重いです。また、フランチャイズ料や廃棄ロスが利益を圧迫する面もあります。
- 外構工事会社: 屋外で重機や手作業による肉体労働が多く、天候に左右されるため体力面で非常に厳しい仕事です。土を掘り、重い資材を運ぶ作業が常で、真夏の炎天下や冬の寒風の中での施工も必要になります。さらに、プロジェクトごとに期限があり、多人数のチームで調整しながら進める必要があるため、管理業務・技術面でもストレスは少なくありません。
このように、収益性だけでなく**「どちらが大変か」**を考えると、常時深夜も稼働するコンビニに比べて外構工事は時間的制約はあるものの、集中して作業できる日中だけの労働です。一方で施工品質を担保するための技術・管理コストや、元請け受注のための営業力も必要です。総合的には、利益面で見れば外構工事会社の方が割に合うケースも多いですが、労働環境や経営リスクをどう捉えるかは経営者によります。
以上を踏まえ、中小企業経営者の皆様には「経営相談」を活用しつつ、必要な経営戦略を講じていただくことをお勧めします。経済産業省の「よろず支援拠点」や中小企業基盤整備機構のチャット相談サービスなどは、経営課題にワンストップで対応してくれる公的相談窓口です。一方で、営業力を強化して売上を増やすことが目的の場合は、営業代行や集客支援を専門に行う企業に任せるのが最も近道です。
営業代行・集客はプロに任せ、月5万円の経営顧問で成功へ導くという考え方が有効です。弊社アルクス株式会社は営業戦略・BPOサービスを全国展開しており、企画から営業実行、分析までワンストップで支援します。岐阜・愛知・静岡・大阪・兵庫・三重・奈良・和歌山・千葉・神奈川・沖縄など全国各地で対面相談が可能な体制を整えており、中小企業の皆様が元請け化を目指すサポートを致します。まずは無料の経営相談窓口で課題を洗い出し、営業代行会社で集客を加速させる。そして月5万円程度の経営顧問契約でPDCAを回す…という組み合わせ戦略をお試しください。それが中小企業の持続的成長と成功への近道となります。
まとめ: 売上拡大や粗利率向上には営業活動が欠かせません。営業代行・集客支援のプロに業務を委託し、自社は工事技術やサービスの品質向上に集中しましょう。同時に、月5万円程度の経営顧問を付けて財務・経営計画を整えれば、安定成長が見込めます。 アルクス株式会社は企業向けの【営業戦略・アウトソーシングサービス】で、多くの元請け化事例を支援してきました。外構工事会社様におかれましても、是非プロの力を借りて、より高いレイヤーでの受注と利益確保を実現してください。
-198-x-50-px-519-x-160-px-198-x-50-px.png?1765598330)

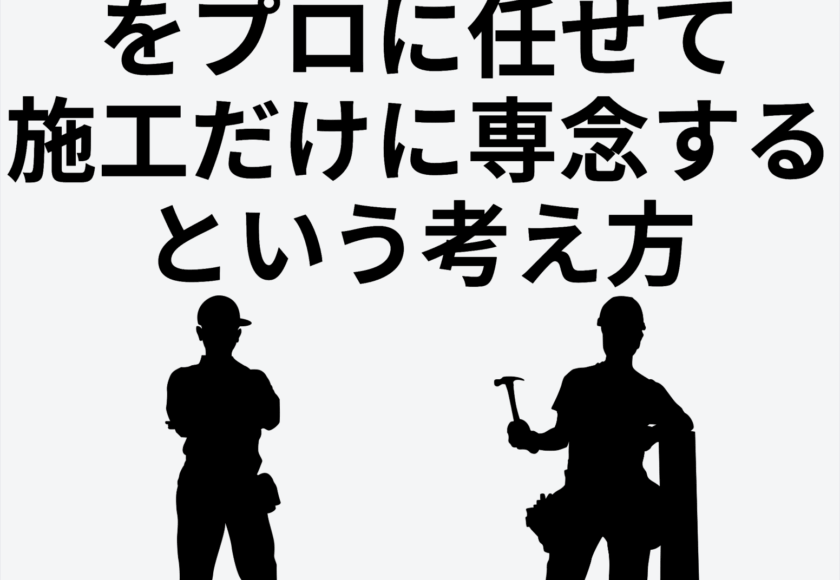
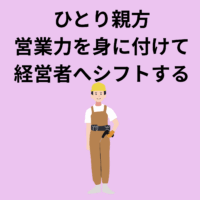
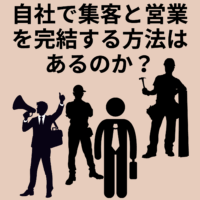




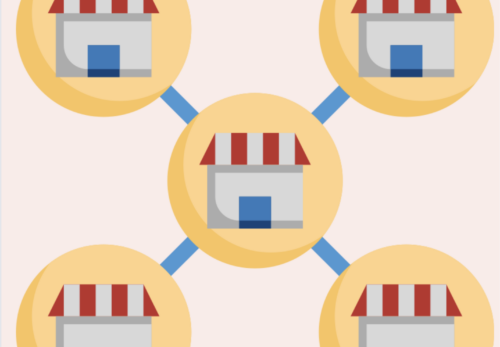
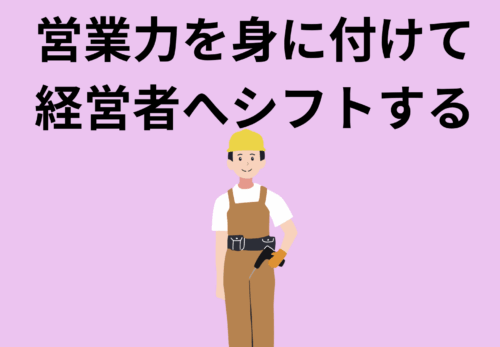
-198-x-50-px-519-x-160-px-519-x-144-px-2.png?1765598330)
この記事へのコメントはありません。